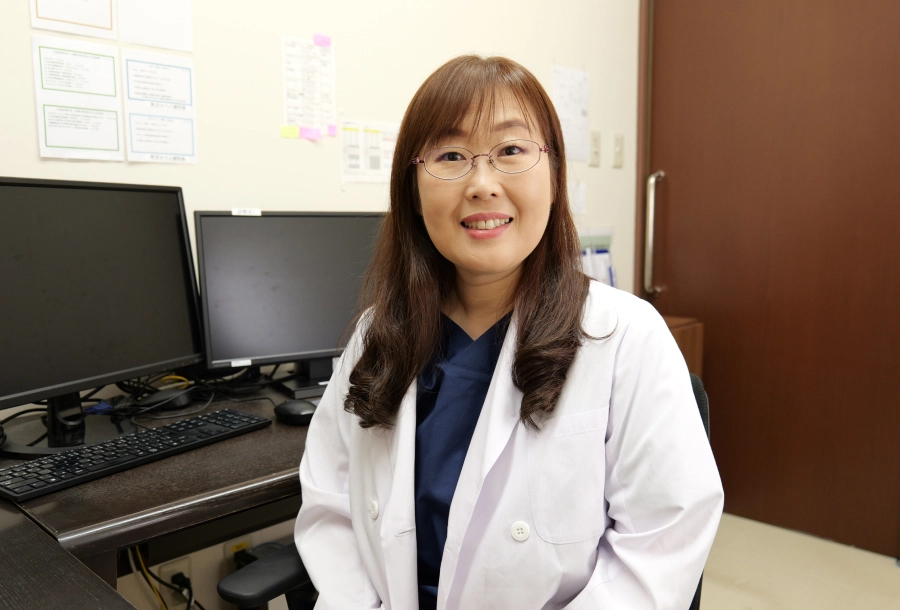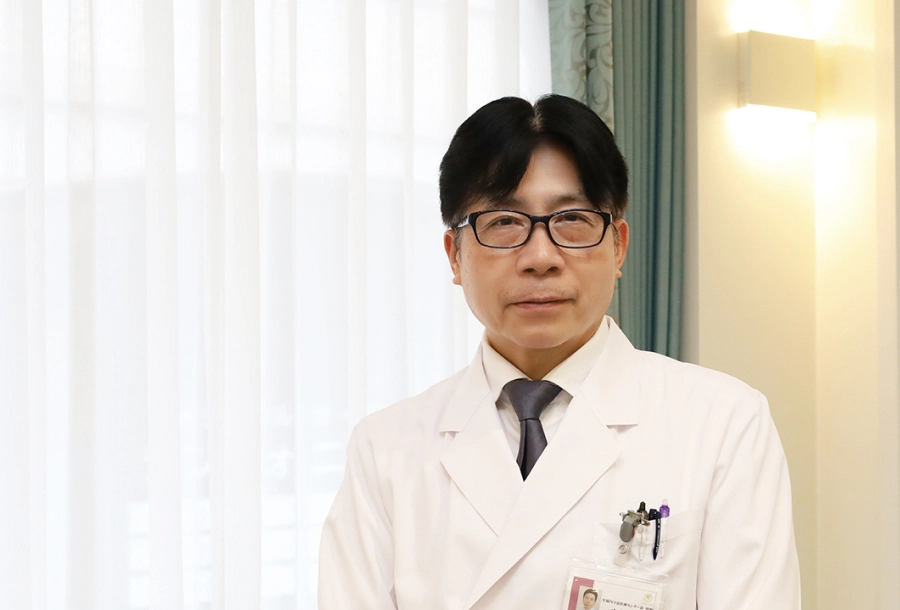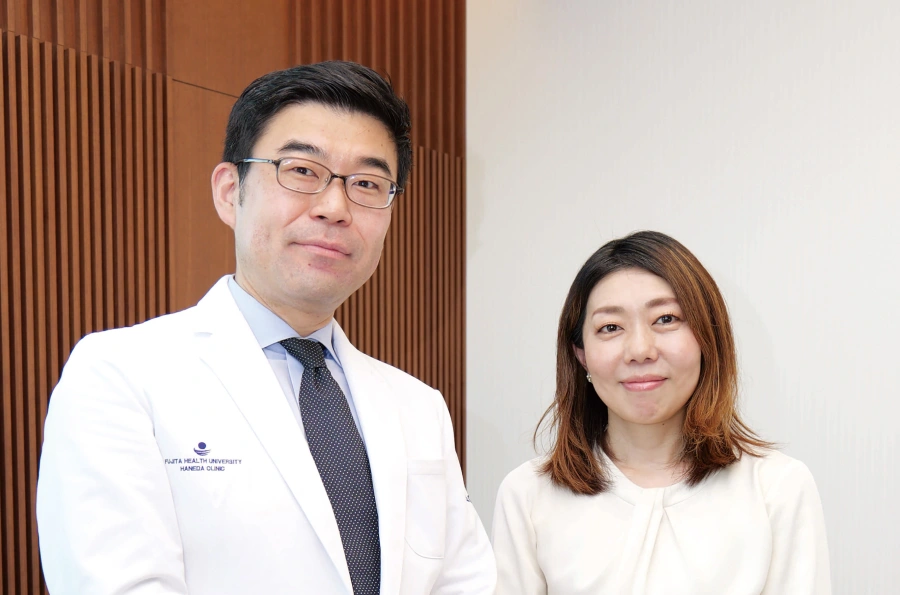公開日
妊娠は時間との勝負
現在の卵巣年齢を把握して
【とくおかレディースクリニック 徳岡 晋 先生】

不妊治療において時間とスピードはとても重要な要素です。なぜなら妊娠できる期間は限られているからです。
とくおかレディースクリニックでは保険診療が始まって以降、30歳前後で来院する方も増え、当然のことですが若ければ若いほど早く妊娠して、卒院する方が多いと言います。一方で年齢が高ければ高いほど妊娠への道は険しくなりがちで、さらに保険を使える回数も半減してしまいます。
治療を迷っているなら、まずは基本検査だけでも受けてみる。ご自身の身体の状態を知ることが将来のライフプランにつながっていくはずです。
誤解も多い
卵巣年齢が示すもの
●不妊治療の現場では「卵巣年齢」という言葉をよく耳にしますが、実年齢よりも卵巣年齢をチェックするほうが大切ということなのでしょうか?
いえ、やはり実年齢は大切ですね。特に35歳のラインは重要です。もちろん個人差があるので、一概に35歳だけで区切れるものではありませんが、一般的に年齢が高くなると妊娠しにくくなります。その大きな要因となるのが染色体異常です。年齢が高くなればなるほど染色体の異常が出てくるため、妊娠しにくくなるのです。
染色体の状態は卵の質に通ずる部分であり、年齢が高くなるにつれて卵の質は低下します。これに対し、卵巣年齢は卵の残り数を示しています。
卵巣年齢について結構勘違いされているのが、卵巣年齢が高いというのは卵子の質が低下しているという意味だと捉えられていることです。
卵巣年齢を知る方法としてAMH値を測定する検査があります。この検査をすれば卵子の質がわかると思っている方が多いのですが、実際にAMH検査でわかるのは、卵巣にあとどれくらい卵が残っているかという数であって、質がわかるわけではありません。あくまでも卵の残り数が多いか少ないかを表しているのがAMHです。ただ、AMHといってもわかりにくいので一般的に卵巣年齢と言われているわけです。表示の仕方も卵があと残り何個と数で示されるのではなく、たとえば「AMHの数値が1ng/mlなら42歳相当」というように診断します。
ですから、まずは実際の年齢を見て、その後に年齢に応じたAMHの値なのか、言い換えると年齢に応じた卵巣年齢なのか、それとももっと若いのか、逆に高めなのかを確認します。
卵巣年齢が若いからOK、ではない
●実際の年齢より卵巣年齢が若く出ることもあるのですね?
はい、あります。ただ、卵巣年齢が実年齢より若いという結果が出たからといって、良かったという話ではありません。卵巣年齢が若く出るケースで多いのが多嚢胞性卵巣だからです。この場合、卵は多く育つし、刺激をすればたくさん採れるのですが、妊娠しやすいわけではありません。むしろ卵の質があまりよくなくて妊娠が難しいことも多いので、AMH値が高いからといって安心材料にはならないのです。
卵はたくさんあるから、わざわざ体外受精をしなくても、タイミングや人工授精を繰り返せば妊娠するのではと思われるかもしれませんが、頸管粘液が少なくて精子が体内に入ってこられないとか、卵の質がよくなくて受精が難しいとか、妊娠は難しい状態なので、AMH値が高く出たときは、何が原因で高く出たのかもきちんと確認する必要があります。
AMHは男性にも伝わりやすい
●では、早めにAMHの検査をすることが大切ですね?
はい、当院では最初の基本検査の時にAMH検査もお勧めしています。その結果、たとえば年齢が38歳で卵巣年齢も高ければ、治療のスピードアップやステップアップが重要だとわかるわけです。
それに保険治療をするなら、40歳になったら胚移植時の保険を使える回数が半減してしまいます。40歳前なら胚移植は6回できるのですが、40歳以上になると3回になるわけですから、卵子の状態から考えても、治療費の面からみても早く治療をスタートすること、それも同じ治療を何回も繰り返すのではなく、適宜ステップアップして妊娠を目指すことがとても大切です。
不妊治療をする上で忘れはならないのは、妊娠は〝時間との戦い〟ということです。可能な限り、早めの妊娠を目指すのが重要なポイントといえます。
AMH検査の結果は当然、ご本人は知っているわけで、ご家庭でご主人にも伝えているはずですが、約20%のご主人しか、AMH値を共有できていないのが現状です。そのため検査、治療となると、のんびり構えている男性が多いように感じます。
それまでは自分の精液検査をして診察を受けて終了とか、あとは奥様のいう通りにタイミングを取る、あるいは人工授精の時に精子を提供するだけという男性がかなり多いです。
ですから月に1度土曜日に開催している勉強会にご主人も参加して、AMHの話などを聞くと、えっと驚かれます。実年齢は32歳なのに卵巣年齢は40歳を超えているケースもありますからね。卵の質が…という話をしてもわかりにくいと思いますが、卵巣年齢の話は○歳と数字で出ますから伝わりやすいのです。
妊娠はいつまでもできるものではなく、時間との戦いなんだと実感することで、不妊治療に対する姿勢も変わってきます。やはり、不妊治療の根幹をなす知識を女性だけでなく、男性もしっかり理解することが何よりも大切です。
男性側の精子は何千万、何億の単位なのに対して、女性の卵子は自然排卵だったら月に1個です。何億に対して1個。仮に男性側の精子に何らかの問題があったとしても、今はいろいろな方法があるので対処できますが、女性の場合はもともと1個な上に時間とともに減っていく。ですから、あといくつ卵があるだろうかと考えたときに、男性も理解しやすいですし、データや数字だと受け入れやすいようです。
月経周期の変化も卵巣年齢を知る手がかりになる
●AMHの他に卵巣年齢を調べる方法はありますか?
卵巣年齢を測る検査としてAMHの他にエコーやFSH、LH、E2(エストラジオール)も挙げられますが、数値化されていてわかりやすい、患者様に一番伝わりやすいのがAMHだと思います。
ただし、以前はAMHの数値が下がり出したら以降は必ず減っていくと言われていたのですが、減少するスピードに変化があると言われ出しました。
実際にAMHの値が1以下だった方が半年後に測ったら低いは低いのだけれど、低下のスピードが予想していたよりゆっくりで、下がり方が少ないということもあります。ゆっくりだから安心していいという話ではありませんがね。
AMHが一番わかりやすいとは思いますが、古くからあるFSH、LHの比率やE2、エコーからも卵巣年齢を確認することはできます。
たとえばFSHなら月経周期3日目の値で確認することが多いですが、若い方の場合、3日目頃には20以下ぐらいに下がるのですが、最初から50、60と上がっていると早い段階で卵が育ち始めているとわかります。 通常、排卵する卵は約3カ月かけて育つのですが、FSHの値が高いケースでは排卵までの期間が短くなるのです。月経周期は一般的に28日と言われますが、時間が狭まって24~25日で排卵するようになると卵が減っているサインと言えます。
更年期になってくると、これと同じ状態で最初は月経周期が短くなってきます。月経周期も卵の残り数、いわゆる卵巣年齢を反映していますからね。そして、いよいよ更年期を過ぎて閉経期に近づくと、ずっと月経が来ない状態になる。こうなると卵はもう少ないので育っていないということになります。

治療はスピード重視
いつ体外受精をするか
●仮に卵巣年齢が高かった場合、どのように治療を進めていくのでしょうか?
それは早く治療することに限ります。患者様にも「治療期間をどれくらいで考えていますか?」とうかがいますが、卵巣年齢が高い場合は体外受精をいつにするかを確認します。仮に半年後に体外受精を考えているなら、その前は人工授精にするのか、タイミングの時期も設けたいのか。
特にご主人が体外受精や人工授精に抵抗を示すケースが多いので、やはり、男性の啓蒙は必要だと感じますね。不妊治療への理解を深めて奥様に協力できるようにするためにも勉強会への参加を強くお勧めしたいです。
あるいは、東京都ならプレコンセプションケアの助成金が女性3万円、男性も3万円が出ます(検査内容は後途)。そういった助成金を利用して精液検査などを受けてみるのもいいかと思います。そして検査結果をもとに今後のライフプランを考えてみる。何歳でひとり目を出産して、ふたり目は何歳で、と。そうやって希望のプランから逆算して考えると、いつタイミングをして人工授精をして…と時期が見えてくるわけです。
仮にタイミング、人工授精を経て1年で妊娠したいということであれば、体外受精は9か月目に設定することになります。1回、体外受精をするには採卵から移植まで3か月くらいはかかりますからね。
勉強会などで妊娠に対する知識がしっかり得られていれば、こうした説明も理解してもらえますし、予想外の返答も返ってきません。
当然のことですが、不妊治療は夫婦お二人の理解と協力が必要不可欠です。治療に通うのは主に奥様になりますから、なおさらご主人の理解は欠かせません。ご主人の役割は奥様のサポートと言えますが、ご自宅で治療の話をしても聞いているような、いないような、治療に積極的ではないと感じるご主人の意識転換に、AMHはとてもわかりやすい要素だと言えます。
着床の窓のずれを調整して妊娠するケースも
●胚移植のポイントというか、先生が治療をしていて感じていることはありますか?
子宮内膜の成熟度のずれ、いわゆる着床の窓のずれについては、いろいろな意見がありますが、私が治療している中では手ごたえを感じています。今まで良好胚を移植しても着床しなかった方に、子宮内膜着床能検査をして時間のずれを調整すると、着床するケースがかなりあるのです。
基本、3回移植するとなったら一番良い状態の胚から移植していくのですが、着床しないとなったら患者様に検査の説明をして、希望される方には検査をしています。その結果、24時間のずれがあった場合にはしっかり補正の時間をかけて成熟を促します。その後で2番目に良かった胚を移植すると2回目で着床するのです。2回目で着床しなくても3回目で着床することもあります。
以前はよく移植の世界、内膜の世界はブラックボックスだといわれていたのですが、こうした検査が出てきて、着床の窓が開いている時に合わせて移植をすると、明らかに妊娠率は上がっています。
質の良い卵を育てる絶対的な方法があったら一番理想的ですが、卵巣の状態、卵の状態は本当に個人差が大きいので、患者様お一人おひとりの状態を見ながら対応していくしかありません。そのためにも現在のご自身の卵巣年齢を把握することは大切です。
卵が必ず採れるという保証はどこにもない
●最後に最近の不妊治療の傾向、特徴として先生が感じていることを教えてください。
以前は不妊治療は35歳を超えてから受ける方が多かったのですが、保険診療が始まって数年、若い方、30歳前後で治療を受ける方たちも増えました。やはり若い方たちは治療をすると短期間で妊娠する方が多いのですが、一方で難治性の方たちが通院するようになったのも、最近の特徴と言えるかもしれません。
AMHが1以下の方たちが本当に多いです。40歳以上で保険を使って体外受精をしていて、他院で2回胚移植をしたけれど妊娠にいたらず、最後の1回は別のクリニックでと来院されたりするのですが、移植があと1回だけと限定されていると治療計画を立てるのが非常に難しいです。
通常なら採卵して、できた胚を戻すわけですが、残り1回なら、それで終わりです。「残っている卵は廃棄して新たに採卵してください」という方もいるのですが、採卵しなおすとしても、次に卵が取れる保証はどこにもありません。卵巣年齢が示す卵の残り数をいかに理解してもらうかが大事だと感じます。
なかには36、37歳でもAMH1以下の方も結構いますから、最初にAMHを確認して治療計画を立てるのはとても大事な点だと言えます。
とくおかレディース
徳岡 晋 先生

経歴
- 防衛医科大学校卒業
- 同校産婦人科学講座入局
- 防衛医科大学校附属病院にて臨床研修
- 自衛隊中央病院(三宿)産婦人科勤務
- 防衛医科大学校医学研究科(医学博士取得課程)入学
- 学位(医学博士)取得(平成12年)
- 平成12年 木場公園クリニック (不妊症専門) 勤務
- とくおかレディースクリニック開設
資格
日本生殖医学会 認定生殖医療専門医
日本産科婦人科学会 認定産婦人科専門医